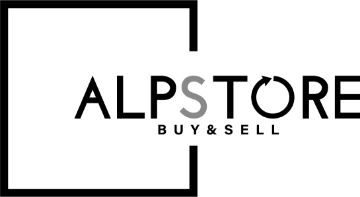昔の日本の金貨「二朱金」とは?朱金の種類や買取のポイントについてご紹介!
「家を整理していたら『二朱』と書かれた金貨が出てきたけれど、これって価値があるの?」
そんな疑問を持つ方もいるかもしれません。二朱金は江戸時代に広く流通していた金貨で、現在でも古銭コレクターから高い人気を誇っています。100年以上前の金貨ということもあり、現存数が少なく希少価値も高いため、高額取引が行われています。本記事では二朱金の特徴や種類、買取価格が高くなるポイントをご紹介します。
見出し
二朱金とはどのような金貨なのか?
江戸時代に流通した小型金貨
二朱金は江戸時代に広く流通した小型の金貨で、貨幣単位「朱(しゅ)」に由来しています。一両の8分の1に相当する貨幣で、小判や一分金に比べて小額なため、庶民の日常生活の細かい取引で多く使われていました。
二朱金の複数の呼び名
二朱金の正式名称は「二朱判(にしゅばん)」ですが、時代や発行地によっては「二朱判金」や「〇〇(元号)二朱判」など、さまざまな呼び方があります。
時代ごとに異なる金の品位
二朱金の価値は金の含有量によって決まりました。特に幕末期は幕府の財政難の影響で金の含有量が減り、種類ごとに品位が大きく異なります。
- 元禄二朱判(1697年):金56.3%、銀43.2%、重量2.23g
- 天保二朱判(1832年):金29.88%、銀69.74%、重量1.64g
- 万延二朱判(1860年):金22.93%、銀76.73%、重量0.75g
二朱金の代表的な種類と特徴
元禄二朱金(げんろくにしゅきん)
1697年から1710年にかけて流通した金貨で、元禄金と呼ばれる貨幣の一つです。品位が高く、美しいデザインで、古銭としての価値も非常に高いです。
天保二朱金(てんぽうにしゅきん)
1832年から1866年に流通し、比較的長期間使用されたため流通量も多く、庶民の間で馴染みの深い金貨でした。金の含有量は低めですが、歴史的価値があります。
万延二朱金(まんえんにしゅきん)
1860年から1869年の間に流通したもので、重量が非常に軽くなったのが特徴です。銀の含有量が金より多く、海外では「万延二朱銀」とも呼ばれました。
甲州二朱金(こうしゅうにしゅきん)
江戸幕府以前、甲斐国(現在の山梨県)を中心に流通していた貴重な金貨です。現存数が少なく、コレクターからの需要が非常に高い種類です。
エラーがある朱金は特に高価
朱金には製造時のミス(エラー)がある場合があります。刻印のずれや重なり、模様が反転しているなど、こうしたエラーがあると希少性がさらに高まり、通常のものよりも高額で取引されます。
- 刻印のずれ:文字や模様が本来の位置とずれているもの
- 刻印の重なり:模様や文字が二重に刻まれているもの
- 逆打ち刻印:表裏が逆転して刻印されているもの
これらのエラーは専門的な知識がなければ判別が難しいため、価値を正確に知るには買取専門店に査定を依頼するのが良いでしょう。
二朱金を高値で売るためのポイント
二朱金を高値で買取してもらうためには、以下のポイントを押さえましょう。
保存状態を良くする
古銭の買取価格は状態が非常に重要です。傷や摩耗が少ないほど高値になります。なるべく清潔な状態で保管しましょう。
付属品や証明書を揃える
購入時に鑑定書や証明書などが付いている場合は、必ずセットで保管して査定に出すと買取価格が上がります。
信頼できる買取専門店に依頼する
古銭の査定は専門知識が必要です。古銭や金貨に詳しい買取専門業者に依頼すると適正な価格で査定してもらえます。是非ALPSTORにご相談くださいませ。
まとめ
二朱金は、江戸時代に広く流通した歴史的価値の高い金貨です。希少な種類やエラー品は特に高額買取の可能性があります。ご自宅に眠っている二朱金を見つけたら、ぜひ査定を受けてみましょう。思わぬ価値があるかもしれません。
ALPSTOREなら無料で査定が出来ますので、気になる方はお気軽にご相談くださいませ。